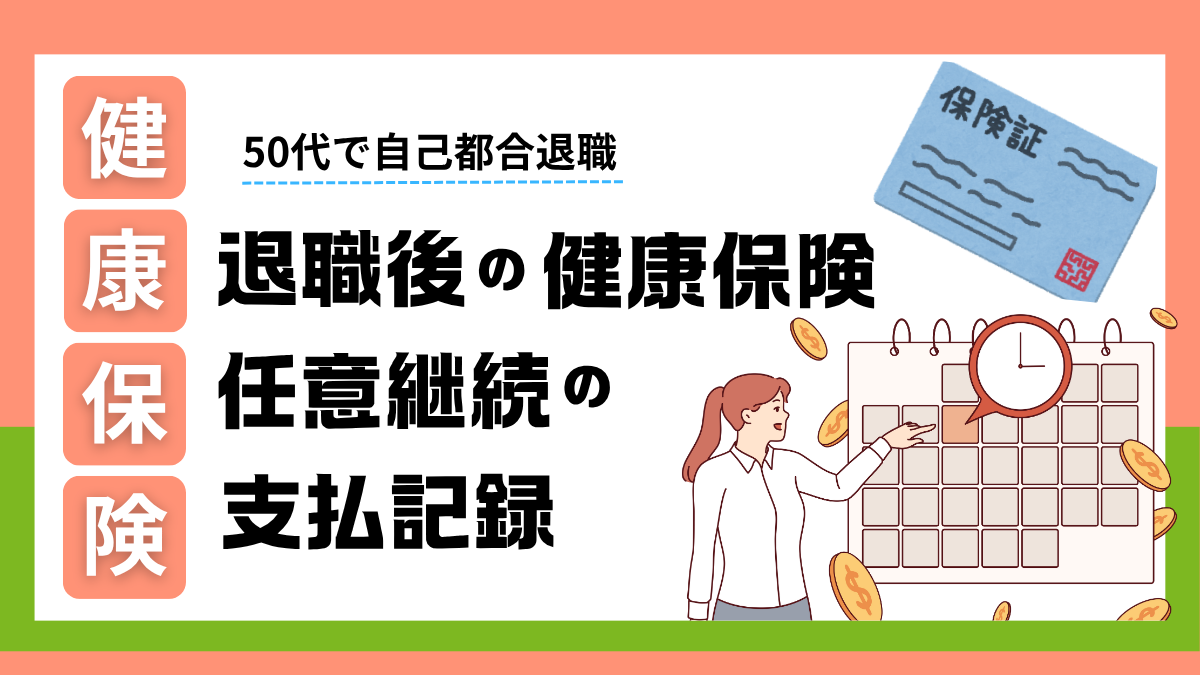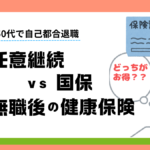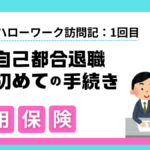退職後、「健康保険任意継続」を選択すると、毎月の支払いを忘れると即資格喪失となるため、非常に注意が必要です。これは、保険料の支払いが資格継続の意思表示とみなされ、直接保険組合に振り込む必要があるからです。
本記事では、52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、最大2年間加入可能な「健康保険任意継続」を選択し、実際に毎月届く納付書を忘れずに支払い続けたリアルな記録です。
「健康保険任意継続」を選択した経緯については、こちらの記事をご覧ください。
※この記事は、私が実際に加入していた健康保険組合での体験に基づいています。詳細はご自身の健康保険組合やお住まいの自治体で必ずご確認ください。また、保険制度は変更される可能性があるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。
健康保険料支払もある無職リアル収支はこちらをごらんください → 退職後の現金収入と支出の記録
「健康保険任意継続」保険料納付の基本
保険料納付方法の選択
「健康保険任意継続」の保険料納付には、以下の2つの制度があります。
私は、前納納付額が高額になるため、毎月支払う単月納付を選択しました。
- 単月納付制度
- 支払期限:毎月10日までに支払う。10日が土日祝祭日の場合は翌営業日となる。
- メリット:費用を抑えられるので計画立てやすい。
- 前納納付制度
- 支払制度:6ヶ月分または12ヶ月分の保険料を納付期限までにまとめて支払う。
- メリット:12ヶ月分を前納の場合、単月納付に比べて約2%程度減額される。
- デメリット:支払額が高額になる。
納付書の取り扱い
- 単月納付制度の場合
納付書は毎月月末に健康保険組合から郵送されます。万が一、月初になっても届かない場合は、必ず健康保険組合に連絡してください。
また、インターネットバンキングなど電子納付する場合でも、納付書は資格継続中である証拠となるため、届いた納付書を確認したうえで支払いを行いましょう。
- 前納納付書の場合
3月末(6ヶ月分と12ヶ月分)と9月末(6ヶ月分)に納付書が郵送されます。
前納希望する場合は、3月末または9月末の納付期限(土日祝祭日の場合は翌営業日)までに振り込みます。私の加入している健康保険組合では、3月26日までに入金が確認できない場合、単月納付書を3日後に送付する仕組みでした。
納入方法
保険料の納付は以下の方法で行います。振込手数料は自己負担になります。
私は取扱銀行と同じ銀行口座を利用していたため、同じ銀行のインターネットバンキングで振込手数料無料でした。
- 銀行窓口
納付書を持参し、窓口で振り込みます。 - インターネットバンキングなどの電子納付
納付書に記載された指定口座に振り込みます。
「健康保険任意継続」保険料支払い記録
毎月の支払い状況や手続きの進捗を追記していきます。また、任意継続が最大2年間の期間満了を迎えた後、国民健康保険への切り替え時期や保険料の変化についても記録予定です。
1回目の支払は、申請後に任意継続被保険者となった月の保険料となるため、支払期限までの日数が短くなる点に注意が必要です。また、年度初めは「前納するかどうかの選択期間」が設けられているため、4月分納付は、納付期限までの猶予が短くなる点にも注意が必要です。
| 支払回数 | 対象月 | 納付書着 | 納付期限 | 猶予日数 | 振込日 | 支払額 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 11月分 | 11/16 | 11/24 | 8日間 | 11/17 | 40,660円 | 40,660円 |
| 2回目 | 12月分 | 11/24 | 12/10 | 16日間 | 12/1 | 40,660円 | 81,320円 |
| 3回目 | 1月分 | 12/24 | 1/10 | 17日間 | 1/1 | 40,660円 | 121,980円 |
| 4回目 | 2月分 | 1/23 | 2/10 | 18日間 | 2/3 | 40,660円 | 162,640円 |
| 5回目 | 3月分 | 2/23 | 3/10 | 15日間 | 3/2 | 40,660円 | 203,300円 |
| 6回目 | 4月分 | 4/2 | 4/10 | 8日間 | 4/2 | 40,660円 | 243,960円 |
| 7回目 | 5月分 | 4/23 | 5/10 | 17日間 | 5/7 | 40,660円 | 284,620円 |
| 8回目 | 6月分 | 5/24 | 6/10 | 17日間 | 6/3 | 40,660円 | 325,280円 |
| 9回目 | 7月分 | 6/24 | 7/10 | 16日間 | 7/1 | 40,660円 | 365,940円 |
| 10回目 | 8月分 | 7/23 | 8/10 | 18日間 | 8/2 | 40,660円 | 406,600円 |
| 11回目 | 9月分 | 8/26 | 9/10 | 15日間 | 9/1 | 40,660円 | 447,260円 |
| 12回目 | 10月分 | 9/24 | 10/10 | 16日間 | 10/1 | 40,660円 | 487,920円 |
まとめ
退職後の健康保険の支払いは、生活設計における重要な要素の一つです。特に「健康保険任意継続」は支払い忘れが資格喪失に直結するため、計画的に進める必要があります。
この記録が、同じ境遇にある方々の参考になれば幸いです。今後も支払い状況や保険の切り替えについて随時更新予定ですので、ぜひチェックしてください。